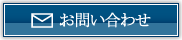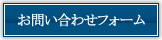親事業者の遵守事項⑨~有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
親事業者は、下請事業者に有償支給材(半製品、部品、附属品又は原材料)を支給している場合に、下請事業者に責任がないにもかかわらず、その有償支給材を用いた納品物に対する下請代金の支払期日よりも先に、有償支給材の代金を回収して、下請事業者の利益を不当に害してはならないとされています。
これは、「有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止」といわれる違反行為です。
親事業者が下請事業者に対して有償支給材を支給することがあると思いますが、その際、親事業者は、当然下請事業者からその代金を回収することになります。
通常の取引であれば、代金の回収時期は、お互いが合意しさえすれば、いつでもよいことになりますが、下請取引の場合、それ自由にしてしまうと、親事業者が有償支給材の代金を直ちに回収することが可能となり、結果として、それで作った給付物の代金を受け取る前に有償支給材の代金の支払いを強制され、下請事業者の資金繰りが苦しくなるおそれがあります。
そのような行為を防ぐのが、この禁止事項の目的となります。
この違反行為のポイントは
①「親事業者の支給する有償支給材」であること
②「有償支給材の代金を先に回収する(支払わせる又は控除する)」とは?
③「下請事業者に責任がある」とはどういうことか?
④「下請事業者の利益を不当に害する」とは?
ということになります。
まず①ですが、条文をみると、「自己(親事業者)に対する給付に必要な原材料等を自己(親事業者)から購入させた場合」となっているので、対象となる有償支給材は、親事業者が売った物に限られるということになります。
なので、親事業者の子会社等が販売するのであれば、この規制の対象にはなりません(ただし、「購入・利用強制」の問題にはなり得ます)。
②ですが、条文を正確に引用すると、「・・・支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価の全部もしくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部もしくは一部を支払わせること」となっておりますので、「控除」と「支払わせる」ということを意味します。「支払わせる」の方は問題ないと思いますが、「控除」とは、テキストによると、「下請代金から原材料等の対価の全部又は一部を差し引く事実上の行為をいい、その結果、支払期日に下請代金を全く支払わないことも含む」とされています。
実際上は、相殺されることが多いと思いますが、民法上の相殺が成立したか否かとは関係がないため、控除という一般的な用語を用いたようです。
下請代金の支払いより先に、有償支給材の代金を支払わせたり、控除したりすると、違反となりますから、少なくとも、下請代金の支払いと同時以降に、有償支給材の代金を回収する必要があります。
実務上は、以下のいずれかの方法になると思います。
ア 下請事業者の給付に対する代金の支払期日に、実際に使用された原材料等の対価を控除して下請代金を支払う。
イ 有償支給材が全部使われる期間を過ぎてから、全額を下請代金から控除して支払う。
アの場合、全部の原材料等が使われていれば、イと同じになりますが、一部しか原材料等が使われない場合には、その代金分だけ回収することになります。
イの場合、原材料等がどのくらい使われたかどうかをいちいち確認しなくてよいことにはなりますが、その分原材料等の対価の回収が遅れることになります。
③の「下請事業者に責任のある場合」については、テキストでは、以下のような場合が該当するとしております。
ア 支給された原材料等を下請事業者が破損又は滅失したため、それを用いて親事業者に納入すべき物品の製造が不可能となった場合
イ 支給された原材料等によって不良品や注文外の物品を製造した場合
ウ 支給された原材料等を他に転売した場合
なお、これは他の違反行為とは違って、例示ですので、これ以外にも該当する場合があると考えられます。
問題は、下請事業者に責任がないにもかかわらず、原材料等が滅失してしまった場合の処理です。
例えば、東日本大震災による津波で下請事業者の工場が被害を受け、全て原材料等が流されてしまったような場合が該当すると思います。
この場合、通常下請事業者に責任はないことになりますから、結局親事業者としては、原材料等の代金を回収できないと考えざるを得ないでしょう。
最後に④ですが、テキスト等では、どのような場合であれば「下請事業者の利益を不当に害する」ことになるのかについて、何ら触れられておりません。
これについては、平成23年の勧告事案が参考になります。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/sitaukekankoku23.files/11122102.pdf
この事件は、早期決済の禁止が勧告の対象となったあまりないケースですが、資料の中に、「下請事業者の不利益」に触れた部分があります。
これによると、「下請事業者の不利益」は
【有償支給原材料等の対価の早期決済と 下請事業者の不利益について】
・S社(勧告を受けた親事業者)が下請事業者に包装材料を有償支給し、当該包装材料を使用した商品に係る下請代金の支払より前に、当該包装材料の対価の決済を行う。【有償支給原材料等の対価の早期決済】
↓
・包装材料の対価の決済後、販売不振等によりS社の自社ブランド商品の製造委託が終了。
↓
・包装材料の使用取りやめに伴い、包装材料が不要となる(残包材の発生)。
↓
・残包材を用いた商品の納入の機会がなくなるため 、下請事業者は残包材を用いた商品の下請代金の支払を受けられず、残包材の対価相当額が下請事業者の不利益として残る。
ということになります。
すなわち、支給された材料の代金は払ったものの、それを用いる製品を親事業者であるS社が製造中止としたため、材料だけが下請事業者の元に残された、これが「下請事業者の不利益」だ、というのです。
もしそうだとすると、「早期決済をしても、最終的に下請代金を支払えば、下請事業者に不利益はない」ということになります。
そう言い切ってよいかどうかは、何ともいえませんが、少なくとも本件では、S社が下請事業者から包装材料を買い戻しておけば、早期決済の部分は勧告の対象とはされなかったように思います。
平成26年度下請取引適正化推進セミナー・事例研究コースのご案内
下記の日程で、下請取引適正化推進セミナー((財)全国中小企業取引振興協会主催)の講師を担当させていただくこととなりました。
今回のセミナーは、過去の下請法違反事例や下請取引改善講習会における質問事例等を題材にした実践的なものとなります。
受講料は1名に付き12,400円(テキスト代・消費税込み)です。
関心のある方は、是非ご参加いただければと思います。
詳しくは、主催者のホームページ(http://zenkyo.or.jp/seminar/orijinal_jirei.htm)をご覧下さい。
記
日時:平成27年3月12日(木) 13:00~16:00
場所:国立オリンピック記念青少年総合センターセンター棟5階501号室(東京都渋谷区代々木神園町3-1)
年末年始の営業のお知らせ
本年は12月26日まで営業の予定です。
平成27年の営業は1月5日からとなります。
よろしくお願いいたします。
親事業者の遵守事項⑧~割引困難な手形の交付の禁止
親事業者は、下請代金を手形で支払う場合、下請事業者に、一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付して、下請事業者の利益を不当に害してはならない、とされています。
これは、「割引困難な手形の交付」といわれる違反行為です。
手形割引とは、「満期未到来の手形の所持人(割引依頼人)が、その手形を第三者(割引人)に裏書譲渡し、その対価として割引依頼人が手形金額から満期までの利息及び費用(割引料)を控除した金額を割引人から取得する行為」(有斐閣・法律学小辞典第4版)のことです。
このように、手形を割り引いてもらうと、割引料等がかかりますから、下請事業者は、下請代金の支払日に満額受け取れないということになりますが、親事業者が下請代金を手形で支払っても、下請代金の減額ということにはなりません(なるのであれば、そもそも、手形で支払うことができなくなってしまいます)。
この違反行為のポイントは
①「一般の金融機関」とは何か?
②「割引困難な手形」とは何か?
③ この違反行為において「下請事業者の利益を不当に害する」とはどのようなことか?
になります。
①については、手形割引を行うのは銀行が多いかと思いますが、銀行に限らず、貸金業の登録を受ければ、業として手形の割引を行うことができます(いわゆる手形割引業者)。もっとも、テキストでは、「一般の金融機関」とは、「預貯金の受入と資金の融通を併せて業とする者」とされ、貸金業者は含まれないとされています。
次の②がこの違反行為のもっとも重要なところです。普通に考えると、ある手形が「割引困難な手形」であるかどうかを一律に定義することは困難でしょう。かといって、個別に判断していたのでは、迅速な処理ができなくなってしまいます。
そこで「割引困難な手形」であるかどうかは、手形期間で一律に判断することとされています。具体的には、繊維業は90日を超える手形、それ以外の業種は120日を超える手形が、この「割引困難な手形」に該当するということになっています。
最後に③ですが、本違反行為は下請法4条2項の違反行為ですので、本違反行為が成立するためには、「下請事業者の利益を不当に害する」という要件も満たす必要があります。これは、上記の期間を満たさない手形(割引困難な手形)を交付したところ、あっさりと割り引きできてしまったような場合に問題になるかと思いますが、過去の指導事例を調べても、実務上、この要件は全く考慮されていないように思います。
従って、公正取引委員会としては、「割引困難な手形」を交付すること自体が、「下請事業者の利益を不当に害する」ことになると考えているのでしょう(か?)。
最後に、全くどうでもいいことですが、下請代金を手形で支払ったはよいが、満期に不渡りとなった場合を考えてみましょう。
この場合、下請事業者は、割り引いてもらった金融機関から、不渡りになった手形の買い戻しを求められることになります。その上で、親事業者に対し、手形金の支払を求めることになるのですが、これによって親事業者は支払遅延になるのか、というのが問題です。
手形法についての理論的な問題は司法試験以来ですので、若干(かなり)怪しいところですが、結論だけ申し上げれば、一旦下請代金を手形で支払ったのですから、遡って下請法上も支払遅延になるということはないように思います。
親事業者の遵守事項⑦~下請代金の支払遅延の禁止②
(4)「受領」と「提供」
支払遅延の起算点となるのが、受領日(役務の場合は提供日)です。受領については、親事業者が目的物を事実上支配下に置いた時点ですが、提供日は、実際に提供のあった日、役務がある程度の期間継続する場合には、その提供が終わった日になります。
従って、その日から60日以内に下請代金を支払わないと、支払遅延となります。
以上が原則ですが、これについては、若干の例外的な取扱いがガイドラインで認められています。
一つが、製造委託の場合です。
物品の製造委託の中には、下請事業者が親事業者の指定する倉庫に物品を預託し、親事業者がそこから随時出庫して使用するという場合があります。この場合、原則からすれば、倉庫に預託した時点で親事業者が受領したことになり、そこから最長でも60日以内に支払わなければならないということになるはずです。
ただ、このようなやり方の場合、下請事業者の生産の都合等で3条書面に記載された納期日前に納品がなされることもありますが、納期日前であっても、一旦受領してしまうと、そこから60日以内に支払わなければならないことになってしまいます。
そうならないために、親事業者からすると、納期日前に納品することは一切認めないという態度をとらざるを得なくなってしまいますが、これは必ずしも下請事業者の利益にならないと考えられます。そこで、以下の要件を満たす場合には、実際に預託した日ではなく、3条書面記載の納期日(納期日前であっても出庫した場合には出庫日)に受領したとする扱いが認められています。
① 納期日前に預託された物品については、親事業者や倉庫事業者を占有代理人とするなどして、下請事業者自ら占有しているという体裁をとること。
② 物品の所有権の移転時期を3条書面記載の納期日とすること。
③ ①と②が親事業者と下請事業者との間であらかじめ書面により合意されていること。
①を満たせば親事業者が自ら支配下に置いた(受領した)ことにならないのか、という点は疑問ではありますが、やむを得ないところでしょうか。
なお、これと似ておりますが、納期を定めず、親事業者が使った時点で受領したとする扱い(いわゆる「コック方式」)は、下請法上一切認められていないのでご注意下さい。
二つ目は、情報成果物作成委託の場合です。
情報成果物のうち、プログラムのようなものは、親事業者の元に納品されても、それが注文通りのものであるかどうかをすぐに判定することは通常困難です。
このような場合も、原則どおり、親事業者が受領した時点から60日以内に下請代金を支払わなければならないとすると、親事業者に酷となる場合も考えられるため、以下の要件を満たす場合には、親事業者が支配下に置いた時点を受領としなくてもよいとする扱いが認められています。
① 注文の品が、性質上、委託の仕様等に合致しているかどうかを外見上明らかにすることができないものであること。
② あらかじめ、親事業者と下請事業者との間で、注文の品を親事業者の支配下に置いた時点ではなく、注文の品が委託の仕様等に合致していることを検査で確認した時点で受領とすることに合意していること。
これは、すなわち、いわゆる検査のための受領を認めるということです。
ただ、この例外的な扱いは、納期を「検査の終了した日」とする扱いまで認めるものではありません。従って、3条書面には具体的な納期日を記載する必要がありますし、その納期日の時点で親事業者の支配下にあれば、検査が完了していなくても、受領したことになります。
三つ目は、役務提供委託の場合です。
役務提供委託も、原則からすると、役務の提供があった日から起算して60日以内に下請代金を支払わなければならないということになります。
ただし、役務には様々な形態があり、例えば、あるビルの清掃作業を月単位で下請事業者に委託するような場合、本来であれば、作業が終わったごとに支払期日を考える必要があることになりますが、それでは親事業者にとって煩瑣となってしまいます。
このため、以下の要件を満たす場合には、月単位で設定された締切対象期間の末日に、役務がまとめて提供されたものとする、という扱いが認められています。
① 下請事業者の提供する役務が同種のものであること
② 親事業者と下請事業者との間で、月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供された役務に対して下請代金の支払いを行うということがあらかじめ合意され、その旨が3条書面に明記されていること
③ 3条書面に、当該期間の下請代金の額又は算定方法が明記されていること
なお、これにより認められる期間は最長でも1月であり、当然ですが、それを超える期間の設定は認められません。
(5)下請代金を振り込みで支払う場合
下請代金の支払いを銀行等の金融機関に対する振込によって行うことは当然認められていますが、暦の都合上、支払期日の末尾が金融機関の休業日に該当してしまうことがあります。
この場合、休業日の前に下請代金を支払えば、当然問題はないのですが、以下の要件を満たす場合には、60日を超える場合であっても、翌営業日払いが認められています。
① 順延する期間が土日など2日以内であること
② 親事業者と下請事業者との間で、下請代金の支払日が金融機関の休業日に該当する場合には翌営業日払いとすることが、あらかじめ書面で合意されていること
(6)その他の注意点
① 請求書の提出遅れ
実務上問題となりやすいのが、下請事業者からの請求書に従って親事業者が下請代金の支払を行っている場合に、下請事業者が請求書の提出を遅らせ、あるいは、請求書の提出を怠ったことにより、親事業者の支払いが遅れてしまった場合でも、支払遅延となるか、ということです。
結論から申し上げると、このような場合でも、公正取引委員会の考え方によれば、支払遅延となります。
親事業者にとって若干酷ではありますが、ご注意下さい。
② 下請事業者の要請により受領日を繰り下げる場合
似たようなケースですが、下請事業者からの要請に従って、受領の時期を遅らせることは認められるのか、という問題もあります。
これも、公正取引委員会の考え方によれば、認められないということになります。
下請事業者のも色々な事情があり、このような扱いを一切認めないということが、はたして下請事業者の保護になるのか、疑問なしとはいたしませんが、下請法とはこのようなものだと割り切っていただくしかありません。