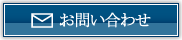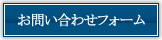カテゴリー : ‘その他’ の一覧
消費税の転嫁対策に関する特別措置法案の公表⑤
6.手続き等
(1)特定事業者の禁止行為(第3条)について
① 指導または助言
公正取引委員会、主務大臣または中小企業庁長官は、特定事業者に対し、第3条に違反する行為を防止し、または是正するために必要な指導または助言をするものとされています。
② 措置請求
主務大臣または中小企業庁長官は、第3条に違反する行為があると認めるときは、公正取引委員会に対し、適当な措置をとるよう求めることができるものとされています。
なお、以下の場合は、この措置請求が義務的となります。
ア 多数の特定供給事業者に対して行われていると認められるとき
イ 特定供給事業者の受ける不利益の程度が大きいと認められるとき
ウ 違反行為を繰り返し行う蓋然性が高いと認められるとき
エ ア~ウの他、消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する重大な事実があると認められるとき
③ 勧告及び公表
第3条に違反する行為を行った特定事業者に対し、公正取引委員会は、速やかに消費税の適正な転嫁に応じることその他必要な措置をとるよう勧告するものとされています。勧告をした場合、公正取引委員会は、それを公表することになります。
勧告については、守らなくても罰則があるわけではなく、従って強制力はありませんが、勧告に従った特定事業者については、独占禁止法の排除措置命令と課徴金納付命令を課さないとすることで、勧告に従うよう促すという構成になっています。
つまり、勧告に従わないと、第3条に違反する行為のうち、独占禁止法の優越的地位の濫用に該当するものについては、そちらに違反する行為として、独占禁止法の手続きが適用されることになるのです。
もっとも、第3条に違反する行為と優越的地位の濫用に該当する行為は、両者の要件が異なる以上、完全に重なるものではありません。第3条に違反する行為であっても、優越的地位の濫用に該当しない行為については、勧告に従わなかった時点でそれ以上の手続きは取り得ないことになります(もちろんそのようなことをお勧めはいたしませんが)。
(2)事業者の禁止行為(第8条)について
これについては、第9条で、第3条に関する手続き(第4条~第7条)が準用されています。
第9条だけだとわかりにくいので、条文を直してみますと、以下のようになります。
(指導又は助言)
第4´条 内閣総理大臣、公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官は、事業者に対し、第8条の規定に違反する行為を防止し、又は是正するために必要な指導又は助言をするものとする。
(公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官の請求)
第5´条 公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官は、第8条の規定に違反する行為があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。ただし、第3号及び第4号に掲げるときは、当該求めをするものとする。
① 当該行為が多数の特定供給事業者に対して行われていると認められるとき。
② 当該行為によって特定供給事業者が受ける不利益の程度が大きいと認められるとき。
③ 当該行為を行った事業者が第8条の規定に違反する行為を繰り返し行う蓋然性が高いと認められるとき。
④ 前号に掲げるもののほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する重大な事実があると認められるとき。
(勧告及び公表)
第6´条 内閣総理大臣は、事業者について第8条の規定に違反する行為があると認めるときは、その特定事業者に対し、速やかにその行為を取りやめることその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
(勧告に係る違反行為についての不当景品類及び不当表示防止法の適用除外)
第7´条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。)第6条の規定は、内閣総理大臣が前条第1項の規定による勧告をした場合において、事業者がその勧告に従ったときに限り、事業者のその勧告に係る第8条の規定に違反する行為については、適用しない。
上記の第7´条によれば、事業者の禁止行為についても、内閣総理大臣による勧告に従わない場合に限り、景品表示法第6条の措置命令の対象となるということになります。
問題は、措置命令が、そもそも第8条の禁止行為に適用できる場合があるのか、ということです。
第8条の禁止行為は、それが事実であれば、不当表示とは考えられません。消費者が消費税を負担しなくて済むかのような誤認をするということはあるのかも知れませんが(個人的にはないと思いますが)、それが「一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示」や「実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」になることは通常考えられないからです。
とすると、第8条の禁止行為については、措置命令の対象にはならないと考えられるため、第3条の禁止行為以上に強制的に取り締まることが困難なものになりそうです。そもそもこれらの行為は、既述のとおり、なぜ取り締まる必要があるのかという根本のところがはっきりしないものであり、取り締まられる側の反発が強いものであることから、仮に違反行為を行っても、確信犯的に勧告に従わない事業者がでることも考えられるところです。
さて、どうなるのでしょうか・・・
消費税の転嫁対策に関する特別措置法案の公表④
※ 平成25年6月5日、消費税の転嫁対策に関する特別措置法が成立いたしました。若干間抜けになってしまいましたが、とりあえず続けます・・・
4.総額表示義務に関する消費税法の特例
消費税の納税義務のある事業者が消費者に対して、価格を表示する場合には、物やサービスの価格に消費税額を加えた価格を表示しなければならないとされています(消費税法63条)。
これに対し、今回の法律では、表示価格が税込価格であると誤認されないような措置を講じていれば、税抜価格を表示してもよいとされました。
これは、今回の消費税率の引き上げが2段階となることから、該当する事業者に総額表示の義務を負わせるのが酷であると考えられたためです。
もっとも、本則は総額表示なので、税込価格を表記しない事業者は、できる限り速やかに税込価格を表示するよう努めなければならないとされています。
なお、税込価格を表示する場合に、消費税の円滑かつ適正な転嫁のために必要があるときは、税込価格に併せて税抜価格または消費税の額を表示するものとされました。
税込価格の表示が定着し、消費税込みであるか否かを示さない価格表示をしている事業者は、ほとんど税込価格を表示しているといえるため、税抜き価格を表示することは、消費税込みの価格と誤認されるおそれがあり、場合によっては不当表示になるおそれもあります(http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/hyoujiqa.html#Q18)。
しかしながら、税込価格が明瞭に表示されていれば、仮に税抜価格を強調するような表示を行っても不当表示には該当しないとされました。もっとも、税込表示が明瞭に記載されているということは、消費者が税抜価格を税込価格と誤認するとは考えられないと思いますから、当然のことのように思います。
5.転嫁及び表示カルテルの適用除外
消費税の転嫁を円滑かつ適正に実行するため、転嫁カルテルと表示カルテルについて、一定の要件の下、独占禁止法の適用を除外することとされました。
転嫁カルテルとは、消費税の転嫁の方法について、複数事業者が共同して、そのやり方を決めることです。典型的には、事業者が本体価格に消費税を上乗せした価格で取引をすることを、参加した全事業者で実施することになります。取引先との力関係から、個別に交渉した場合は消費税の転嫁を行えない場合であっても、複数の事業者が共同でそのような申し入れをすれば、転嫁を認められやすくなるであろうということからこのようなカルテルが認められることになったのです。端数を切り下げるのか切り上げるのかなどについて共同で行うこともここに含まれます。
なお、当然のことですが、転嫁の方法とは関係のない本体価格を統一する決定は適用除外の対象外となります。
この転嫁カルテルが認められる要件は、
① 共同行為に参加する事業者の3分の2以上が中小事業者であること
② 不公正な取引方法を用いるものではないこと
③ 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするものではないこと
④ 一定の取引分野における競争を実質的に制限することによって不当に対価を維持したり、引き上げたりするものでないこと
⑤ 公正取引委員会へ届け出ること
です。
表示カルテルとは、消費税についての表示の方法をどのようにするかについて、複数事業者が共同して決めることです。
例えば、税率引き上げ後の価格の表示について、以下のような統一的な方法を用いるようにすることです。
・「税込価格」と「消費税額」を並べて表示する。
・「税込価格」と「税抜価格」を並べて表示する。
この表示カルテルが認められる要件は、上記の②~⑤になります。
消費税の転嫁対策に関する特別措置法案の公表③
3.事業者がしてはならない行為
平成26年4月1日以降、事業者(特定事業者ではありません)は、自己の供給する商品または役務の取引について、以下の表示をしてはならないとされています。
①取引の相手方に消費税を転嫁しないとの表示
②取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部または一部を対価から減ずるとの表示であって消費税との関連を明示しているもの
③消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって、①②に掲げる表示に準じるものとして内閣府令で定められた表示
ご存じのとおり、今回の法律の中で、もっとも反対の多い部分となります。余りにも反対意見が強いので、法律案も見直され、②については当初のものに「消費税との関連を明示しているもの」という部分が追加されました。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
詳細は夏頃に公表予定のガイドラインによることになりますので、ここでは、概要と問題点について触れたいと思います。
(1)相手に消費税を転嫁しない旨の表示(①)
事業者は、取引の相手方に消費税の転嫁をしていない旨の表示をしてはなりません。
例えば、
・当店では消費税をいただいておりません。
・消費税は当店で負担しております。
といった表示は、禁止されることになります。
(2)消費税額の全部または一部を減額するとの表示であって消費税との関連を明示しているもの(②)
事業者は、取引の相手方が負担すべき消費税の全部または一部を値引きするような表示をしてはなりません。
例えば、
・表示価格から消費税分の8%を値引きします。
といった表示をしてはならないことになります。
ただし、前述のとおり、「消費税との関連を明示していること」という要件が付加されたので、
・表示価格から8%値引きします。
という表現は認められることになりました。
(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示
事業者は、対価そのものではなくても、消費税に関連して相手方に経済上の利益を提供するとする内容の表示をしてはなりません。
例えば、
・消費税の8%分ポイントアップ
といった表示は禁止されることになります。
具体的にどのような表示が禁止されるのかは、内閣府令で定めることになっているので、現時点では不明ですが、①及び②に準じるものとなっていることから、これについても消費税との明示的な関連性が要求されるとすると、単に「8%分ポイントアップ」とするだけでは、違反表示にならないかも知れません。
(4)問題点
前述のように、本条項は特にもっとも影響を受けると考えられる小売業界からの反発が強く、法案の修正を余儀なくされました。なぜ反発を招いたのかといえば、直接には業績への悪影響への懸念からだと思います。
消費税引き上げ後に予想される業績への悪影響、すなわち売上の減少に対処するため、小売業界の側とすれば、いわゆる消費税還元セールの類を実施し、売上の減少を抑制したいと考えていたところ(事実前回の引き上げ時には、これにかなり効果があったようです)、それらの販売促進や広告の表現が制約されることになるからです。
もちろん、こういった表現を制約するきちんとした理由があれば、制約を受けてもやむを得ないといえるのですが、これらの条項を導入しなければならない理由というものに、余り説得力がないということも、規制に対する反発の原因になっているようです。
反発を招いた規制の理由ですが、当初は、このような表示を認めると消費税の転嫁に悪影響があるから、とされておりました。すなわち、消費税を取らない、その分値下げするといった表示をした業者は、納入業者に消費税を支払わないことになるので、適切な転嫁を行うためには、これらの表示を禁止する必要があるというのです。対象は事業者ですが、特定事業者の禁止行為の予防的な規定と位置づけられているというわけです。
もっとも、これだけでは、全ての事業者を対象としているということを説明しづらいですし、特定事業者をしっかり監視すればよく、商売のやり方にまで口を出すのは行き過ぎではないかという、もっともな指摘を受けることになります。
そのような指摘に対する反論も難しいと考えたのか、その後は、消費税を納めなくてもよいかのような誤解を生む表現を避けることが理由であるとされたり、消費税の税収を上げるのに悪影響があるからということが理由とされたりしているようです。
どうやら、消費税還元セールの類を行うと、消費者が消費税は納めなくてもよいと誤解したり、消費税の税収が上がらなくなったりすると政府は考えているようですが、この理屈も裏付けるデータがないと、にわかに賛同しがたいといわざるを得ません。
消費税を転嫁するかは、基本的には相対当事者間の契約で決めるべき問題なので、自分からいらないというのも、基本的には自由のはずです。従ってそれを売り物にして商売をするというのも、当然自由であるべきだと思います。そういった点から見ても、本条項には疑問が残るといわざるを得ません。
なお、反対の声に配慮した、「消費税との関連を明示している」との修正ですが、詳しくはガイドラインを待つ必要があるものの、「消費税」という文言さえ使わなければ全ていいということにはならないとすると、その線引きは極めて難しいものにならざるを得ないと思います。
詳しくはガイドライン等を待ちたいと思います。
消費税の転嫁対策に関する特別措置法案の公表②
2.特定事業者がしてはならない行為
平成26年4月1日以降、特定事業者は、①減額、②買いたたき、③購入・利用強制、④税抜き価格による交渉拒否、⑤報復措置をしてはならないとされています。
(1)減額
特定事業者は、商品若しくは役務の対価を減額して、特定供給事業者による消費税の転嫁を拒んではいけないとされています。
減額というのは、一旦決まった対価を減らすことなので、消費税率引き上げにより、価格を据え置くのではなく、さらに代金を削るという行為が対象になります。
一方、「消費税の転嫁」ですが、消費税法上、転嫁については規定がないので、用語の意味が問題になります。通常は本体価格に消費税分を上乗せして取引の相手方に支払ってもらうことを意味すると考えてよいでしょう。
この転嫁を拒むというのですから、典型的には、消費税率が上がったことを理由として、その分を対価から減じることになるでしょう。全額であれば当然ですが、消費税相当額全額ではなく、一部についてであっても減額することも含まれると考えられます。
消費税込みの価格であれば、それを減額した場合、結果としてそこに含まれる消費税額も、少なくとも一部は減ることになりますから、この減額に該当するということになるでしょう。
問題は、本体価格は減額するが、それに対する消費税額はきちんと8%支払うという行為が、この「転嫁を拒む」に該当するのかどうかです。
言葉の解釈からすれば、含まれないと考えることになるのでしょうが(後は、それが下請法や優越的地位の濫用に違反するかどうかが問題になるかどうかです)、それでよいのかは検討の余地がありそうです。
夏頃までにガイドラインが作成されるようなので、この点についても、そこで明らかになるでしょう。
なお、下請法同様、相手方が同意しても、消費税の転嫁を拒むための減額は違法になるという運用になると思います。
(2)買いたたき
特定事業者は、商品若しくは役務の対価の額を当該商品若しくは役務と同種若しくは類似の商品若しくは役務に対し通常支払われる対価に比し低く定めることにより、特定供給事業者による消費税の転嫁を拒んではいけないとされています。
これは、対価を決めるに当たって、通常支払われる対価に比べて低い価格を設定し、消費税の転嫁を拒むことを禁止する規定です。
既に適正に定められた価格であっても、消費税率引き上げ後、それを見直して、消費税を適正に転嫁するようにしないと、場合によってはこの買いたたきに該当することになります。
下請法に同様の規定がありますが、下請法は、「著しく低い下請代金」を「不当に定める」と違法となります。
一方こちらの方は、「著しい」という部分と「不当に定める」という部分が削られています。従って、代金を決めるに当たって通常支払われる価格に比べて安い価格にすることにより、消費税の転嫁を拒むと直ちに違法ということになるでしょう。
問題は、どのように対価を決めたら「消費税の転嫁を拒んだ」ことになるのか、です。
減額と違い、対価を決める行為ですから、税込で対価を決めた場合、そのうちの8%が消費税分だとすれば、転嫁を拒んだと認定することは困難ではないかと思います。
一方、税抜きで対価を決めた場合、それに対する8%未満の額しか加えないような価格設定をすれば、当然この買いたたきになると思います。
ただ、同じ価格でも、本体価格を低めに設定し、それに対する消費税額として8%を加えるようにすれば、減額の場合同様、消費税の転嫁を拒んだとはいえないと考えられます。
「通常支払われる対価」という要件は、下請法の場合と同様、余り機能しないと考えられるため、やり方次第で同じ金額でも結論が異なるということになりそうですが、これは、よろしくないように思います。
これも、ガイドラインがどのように処理するのかを待ちたいところです。
(3)購入・利用強制
特定事業者が、特定供給事業者による消費税の転嫁に応じることと引換えに、自己の指定する商品を購入させ、若しくは自己の指定する役務を利用させるとこれに該当します。
あくまで消費税の転嫁に応じることと引換えですから、消費税の転嫁と無関係に購入・利用を強制する場合は含まれないことになります(もちろん下請法などの問題は残りますが)。
一方で、消費税の転嫁に応じることと引換えにして購入・利用を強制すればいいのであって、実際に転嫁に応じたかどうかは無関係になると思います(結果として応じなかった場合には、減額、買いたたきなど、別の問題が生じます)。
(4)不当な経済上の利益提供要請
特定事業者は、特定供給事業者による消費税の転嫁に応じることと引換えに、又は自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させてはいけないとされています。
これも消費税の転嫁に応じることと引換えとなっているため、消費税の転嫁と無関係に経済上の利益の提供を要請することは、この禁止行為とは無関係になります。
(5)税抜き価格交渉の拒否
特定事業者は、商品又は役務の供給の対価に係る交渉において、特定供給事業者から消費税を含まない価格を用いたいとの申出があった場合、それを拒んではならないとされています。
これは、消費税を含まないものとして価格について協議し、最後に消費税額を加えれば、きちんと転嫁されたか否かがはっきり分かるため、消費税の適正な転化を促進するためには有効であるとして設けられた規定だと考えられます。
消費税法63条は、これとは逆に小売業者は税込の価格表示をしなければならないとしておりますから混乱しますが、消費税法の規定は消費者に対して実際の買値をきちんと示すという趣旨であり、こちらは消費税を適正に転嫁するための規定なので、特に矛盾しているわけではありません。
ただ、前述のように、消費税を含まない価格を用い、転嫁自体はきちんと行っていたとしても、肝心の価格が適正かどうかは少なくともこの法律の問題ではないので、これで大丈夫というわけにはいかないように思います。
(6)報復行為
特定事業者は、特定供給事業者が(1)から(5)までに掲げる行為があるとして公正取引委員会、主務大臣又は中小企業庁長官に対し、その事実を知らせたことを理由に、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをしてはならないことになっています。
このような規定がないと、報復行為をおそれた特定供給事業者が泣き寝入りになってしまうため、設けられた規定です。
消費税の転嫁対策に関する特別措置法案の公表①
平成25年3月22日、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案」(消費税の転嫁対策に関する特別措置法案)が閣議決定され、公表されました
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/mar/130322.html。
同法案は、以下の4つの特別措置を主な内容とするものです。
1 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
2 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
3 価格の表示に関する特別措置
4 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
上記の特別措置については、特に2を中心に小売業界の反発の声が強く、はたして法案どおり実施できるかどうか予断を許さないところで、注目もこの部分に集中しているようです。
ただ、本稿では、そこのみにとらわれず、全体の内容を冷静に検討してみたいと思います。
1.当事者
この法律に登場するのは、「特定事業者」「特定供給事業者」「中小事業者」です。
(1)特定事業者
まず特定事業者は、以下のいずれかです。
① 大規模小売事業者
② 特定供給事業者から継続して商品または役務の供給を受ける大規模小売事業者以外の法人事業者
①の大規模小売事業者は、公正取引委員会規則で定めることになっているので、現段階では正確に分かりませんが、「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」によれば、「大規模小売業者」とは、コンビニなど、フランチャイズ・システムによる場合を含む小売業者で、以下のいずれかに該当する者をいうとされているので、参考になると思います。
a 前年度の売上(加盟者の売上を含む)が100億円以上である者
b 床面積が1500平方メートル以上(東京23区及び政令指定都市にあっては3000平方メートル以上)の店舗を有する者
②は、大規模小売事業者ではないものの、特定供給事業者(資本金3億円以下の事業者(個人も含みます))から継続して商品または役務の供給を受ける法人事業者が該当することになります。
(2)特定供給事業者
特定供給事業者は、以下のいずれかの法人事業者です。
① 大規模小売事業者に継続して商品または役務を供給する事業者
② 大規模小売事業者以外の特定事業者に継続して商品または役務を供給する資本金3億円以下の事業者(個人を含む)
(3)中小事業者
中小事業者は、以下のいずれかになります。
① 主として製造業、建設業、運輸業などの事業(卸売業、サービス業、小売業は除く)を営む資本金3億円以下の会社とこれらを営む従業員数300人以下の会社と個人
② 主として卸売業を営む資本金1億円以下の会社とこれらを営む従業員数100人以下の会社と個人
③ 主としてサービス業を営む資本金5000万円以下の会社とこれらを営む従業員数100人以下の会社と個人
④ 主として小売業を営む資本金5000万円以下の会社とこれらを営む従業員数50人以下の会社と個人
⑤ その他政令で定める会社と個人