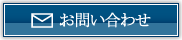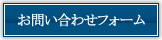フランチャイズ契約上の競業避止義務②
5.潜脱行為の防止
③は難しい問題です。実務上特に問題になるのは、競業を行う主体の問題です。契約に拘束されるのは契約当事者ですから、フランチャイズ契約の当事者以外の者が競業を行ったとしても、それをフランチャイザーが禁止することは原則としてできないことになります。もっとも、そうだとすると、例えばフランチャイジーが別会社を設立して競業を行ったり、フランチャイジーの役員やその親族などが競業行為を行ったりした場合に、フランチャイザーとしては何の手も打てないことになってしまいます。
このような不都合に対処するため、通常は、フランチャイジーに対し、その子会社や役員など、フランチャイジーと一定の関連を有する人に対して、競業行為を行わせないような義務を、フランチャイズ契約上課していることが多いようです。このような契約条項も一般に有効だと思いますが、関連性の立証が困難であることも多く、また直接違反行為者に対して競業行為の差止を求めることができないため、実効性という点では今ひとつになってしまいます。
6.実効性の確保
(1)フランチャイザーが執りうる手段
④の実効性の確保についてですが、これは、契約で規定したことをどのようにしてフランチャイジーに守らせるのかの問題になります。競業禁止規定にフランチャイジーが違反した場合、フランチャイザーとして執りうる手段は、
a 競業行為の差止請求
b 損害賠償請求
なので、競業禁止規定の実効性を確保するということは、それぞれの請求をどうやって効率的、効果的に行うのかという問題になるでしょう。
なお、競業行為の差止と損害賠償請求は、それぞれ別個の権利なので、両立しうることになります。すなわちフランチャイザーとしては、競業行為の差止を求めつつ、損害賠償を請求することができるのです。
(2)差止請求の問題点
① 競業行為の特定
まず、aの競業行為の差止請求ですが、これを行うにあたっては、競業行為に該当するのはどのようなものかを明確にすることが必要になります。
競業行為については、前述のとおり、フランチャイズ契約書上「類似または競合する事業」などと記載されることが多いのですが、実際に差止請求をする場合には、違反行為を特定し、それを文章化しなければなりません。
なお「類似または競合」という文言では、本当にそれに該当するかどうかという点で解釈が分かれる場合があります。そこで、契約書上、一定の行為について具体的に記載し、それらは競業行為に該当するとみなすとか、「本契約において競合する事業とは○○のことをいう」といった規定を設けておく方法がとられることもあります。
② 競業を禁止する期間
フランチャイズ契約終了後にどの程度の期間、元フランチャイジーに競業行為を禁止できるのかは悩ましい問題です。フランチャイザーの側からすれば、できるだけ長い期間、元フランチャイジーの競業行為を制限したくなるところですが、余りに長期間競業行為を制限することは、元フランチャイジーの職業選択の自由を過度に制約することになり、適当ではないと思われます。また、フランチャイザーにとっても、ノウハウの保護が主な目的であることから、それほどの長期間競業を禁止しなくても目的は達成できると考えられます。
このため、フランチャイズ契約上は、契約終了後の競業禁止期間を、前述のとおり、1~3年程度とすることが多いのです。無期限の競業避止義務は、少なくとも一定期間を超える部分については、無効とされる可能性が高いでしょう。
このように、契約終了後の競業禁止については、期間が制限されることになるのですが、このことは実務上やっかいな問題を引き起こします。元フランチャイジーが契約終了後に競業行為を行った場合、フランチャイザーとしては、その差止を求めて訴訟を提起することになりますが、この訴訟も、すぐに判決が出るわけではなく、第1審から上告審まで争われた場合、3年以上の期間が経過してしまうことも珍しくありません。もし、判決までに競業禁止期間が経過してしまえば、フランチャイザーは敗訴ということになります。勝訴の判決をもらったとしても、強制執行で差し止めるまでに期間が経過してしまえば、やはり実際に差止をすることはできなくなってしまうでしょう。
このような場合のための法的手続きとして、保全処分というものがあります。これは、時間のかかる本案の判決が確定する前に、仮の処分として営業を差し止めてもらうための手続きです。仮の処分であるため、裁判所の判断は迅速に出されるのですが、通常の訴訟とは違い、単に競業禁止違反の行為があるだけでは足りず、「保全の必要性」という要件も必要とされることになります。
これは、「仮に現時点で競業を停止しておかないと、フランチャイザーに回復できない損害が生じるおそれがあること」ですが、これを裁判所に示すことは容易ではないと思います。逆に、元フランチャイジーの営業を止めてしまうと、そこで雇用されている従業員を解雇せざるを得なくなるなど、仮に、判決で元フランチャイジーの側が勝訴しても、元フランチャイジーの側に回復困難な損害を与えるおそれもあるため、保全処分で営業の差止を求めることは、通常難しいといわざるを得ません。
フランチャイズ契約上の競業避止義務①
1.競業避止義務条項の趣旨
フランチャイズ契約では、競業避止義務条項を設けることが通常です。競業避止義務条項が設けられる理由は、企業秘密やノウハウの保護、顧客の誤認防止などですが、守秘義務条項やノウハウの流用禁止条項だけでなく、なぜ、競業避止義務条項が必要になるのかといえば、企業秘密やノウハウ、特に後者については、その内容や侵害(流用)の有無・程度を権利者において正確に判断し、主張・立証することが難しいからです。
フランチャイズ・システム、特にいわゆるビジネス・フォーマット型といわれるフランチャイズ・システムにおいては、フランチャイジーに対するノウハウの提供が契約における主要な柱となっていますが、本来秘密であるはずのノウハウがフランチャイジーに開示されてしまうため(のみならず、それを使って商売ができるように指導まで受けられます)、フランチャイザーにおいては、より一層その保護が重要になるのです。にもかかわらず、違反行為を明確にすることが困難であるとするとフランチャイザーが困るので、ノウハウの開示後、競合する事業という外見上比較的判別の容易な指標を設け、これを行えばノウハウの侵害があるものと擬製したのです。
なお、競業避止義務については、フランチャイズ契約期間中のものとフランチャイズ契約終了後のものに分けられますが、実務上は、契約終了後の方が問題になることが多いといえるでしょう。契約期間中は、違反行為によってフランチャイズ契約が解除されてしまうリスクがあるからです。
2.フランチャイズ契約書上の競業避止義務条項
フランチャイズ契約書上の競業避止義務条項を考えるに当たっては、以下のような点が重要になります。
① そもそも「競業」を禁止してもよいのか。
② 禁止しうるとして、何をどの程度禁止すればよいのか。
③ フランチャイジーの潜脱行為をどうやって防ぐのか。
④ どうやって実効性を確保するのか。
3.競業禁止の可否
①についていえば、フランチャイジーの競業を禁止する趣旨が上記のようなものであることから、通常は、合理的な範囲でフランチャイジーの競業を禁止することは、フランチャイズ契約終了後のものも含めて許されると考えられており、過去の裁判例においても、競業避止義務条項は通常有効なものとして扱われています。
4.禁止の程度
(1)禁止の限界
②については、フランチャイザーの側からすれば、できるだけ多くの(長期間の)制約を課したいということになりますが、一方で、フランチャイジーの側からすると、特に契約終了後に長期間競業を禁じられることは、事業経営上大きな制約となり、場合によっては、その職業選択の自由を侵害することになりかねません。そこで、競業を禁止できるとしても、自ずと限界があることになります。
(2)禁止される「競業」とは
まず、何を禁止するのかですが、これは当然「競業」になります。契約書上の表現としては、「本件店舗における事業と競合する事業」などと表記されることが多いと思いますが、これについては後述します。
(3)フランチャイズ契約終了後の競業禁止の期間
フランチャイズ契約終了後の競業避止義務については、どの程度の期間競業を禁止すべきか、ということも問題になります。これも、フランチャイザーの側からすれば、競業行為によって生じる不利益を回避するのに必要十分な期間ということになります。具体的に何年間がこれに該当するのかは業態ごとに異なるため難しいものと思いますが、通常は1年~3年とする例が多いようです(もちろんこれでなければならないということはありません)。なお、期間の設定の仕方についても後述します。
平成24年度下請取引改善講習会のご案内
下記の日程で、下請取引改善講習会((財)全国中小企業取引振興協会主催)の講師を担当いたします。
受講料・テキスト代ともに無料ですので、下請法に関心のある方は、是非ご参加いただければと思います。
詳しくは、主催者のホームページ(http://zenkyo.or.jp/seminar/course.htm)をご覧下さい。
記
1 平成24年6月18日(月)愛知県名古屋市(愛知県産業労働センター)
2 平成24年7月6日(金)東京都千代田区(日本教育会館)
3 平成24年8月6日(月)東京都江東区(東京ファッションタウンTFT)
※時間は、1が13:30~16:30、2及び3が9:30~16:30となります。
平成24年度下請取引適正化推進セミナー(基礎コース)のご案内
下記の日程で、下請取引適正化推進セミナー(財団法人全国中小企業取引振興協会主催)の講師をいたします。
いずれも下請代金支払遅延等防止法の初心者向けの解説で、有料(1名1会場12,000円)となります。
申込方法など詳しくは主催者ホームページ(http://zenkyo.or.jp/seminar/yuryo.htm)をご覧下さい。
記
1.平成24年5月22日(火)東京都江東区(東京ファッションタウンTFT)
2.平成24年6月6日(水)東京都江東区(東京ファッションタウンTFT)
※時間はいずれも13:00~16:30です。
FC法務研究会のお知らせ
平成24年5月16日午後2時から、株式会社アクアネット(http://aqnet.co.jp/)主催のFC法務研究会で講師を務めます。
競業避止義務など、本部のノウハウの保護についてお話しさせていただく予定です。
有料のセミナーになりますが、関心のある方は是非ご参加下さい。