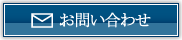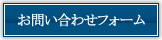年末・年始休業のお知らせ
当事務所の年末・年始の休業は、平成24年12月31日から平成25年1月4日までとさせていただきます。
年内の営業は12月28日まで、新年は1月7日からの営業となります。
よいお年をお迎え下さい。
小売業と下請法
(1)平成24年9月に下請法違反で公正取引委員会から勧告が4件出されました。
① http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.september/12090701.pdf
② http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.september/120920.pdf
③ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.september/12092102.pdf
④ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.september/120925.pdf
①~③の違反者の事業は小売業、④の違反者の事業は、違反者の会員である小売業者への商品供給事業になります。
下請法というと製造業が対象のようですが、下請法の適用のある取引の一つである「製造委託」には、事業者が業として行う販売の目的物たる物品の製造を他の事業者に委託することが含まれますので、物品の販売をしている小売業者は(もちろん④のような卸売業者も)、下請法が適用される場合もあるのです。
特に最近はやりのPB商品は、まさに自社向けの商品として製造を委託しているため、製造委託に該当することになります(もちろんその他の要件があるため、直ちに下請法の適用があるわけではありませんが)。
また、小売業については、仕入や返品に独特の商習慣がありますが、下請法に違反するものについては、当初から契約で定めていても認められないため、注意が必要になります。
(2)違反行為について
①の違反行為は「下請代金の減額」「返品」「不当な経済上の利益の提供要請」
②の違反行為は「下請代金の減額」「不当な経済上の利益の提供要請」
③の違反行為は「下請代金の減額」「返品」「不当な経済上の利益の提供要請」
④の違反行為は「下請代金の減額」「返品」「不当な経済上の利益の提供要請」
です。
通常勧告の対象となるのは「下請代金の減額」がほとんどなのですが、「返品」や「不当な経済上の利益の提供要請」も勧告の対象となっているのが特徴といえるでしょう。特に④の「返品」については、会員による販売期間が終了したものを下請事業者に引き取らせていたのですが、返品した商品については、原則として次の販売期間開始時に再納品させることを条件としていたようです。もちろんこのような合意があっても返品が認められるわけではありません。
なお、④については減額分の返還と支払遅延による遅延利息の支払いの合計で約39億円にもなりました。
繰り返しになりますが、下請事業者が合意しているからといって、下請法の違反を免れることはできません。下請法違反とされることのないよう、十分な理解が必要になります。
夏季休業のお知らせ
当事務所は、8月15日から17日まで、夏季休業とさせていただきます。
フランチャイズ契約上の競業避止義務③
③ 契約上の対処
契約終了後の競業禁止期間が有限であるという問題に対処する方法として考えられるのは、
ア 競業禁止期間の開始時期を遅らせる。
イ 容易に競業に踏み切れないようにする。
というものです。
まずアですが、これは、競業禁止期間の開始時期を、フランチャイズ契約終了の際に、フランチャ契約上実行することがフランチャイジーに義務づけられている作業を全部終えた時点からにするというやり方です。
通常、競業禁止期間の開始時点は、「フランチャイズ契約終了の日から」となっていることが多いと思いますが、この場合、契約終了の時点で既に違反行為を行っている場合であっても、それとは無関係に競業禁止の期間が進行することになってしまいます。
期間の長さ自体に前述のような制限があるので、これに対処するには期間の開始事前を遅らせることしかありません。そこで、フランチャイズ契約上、フランチャイズ契約終了後の競業禁止期間の開始時点を、元フランチャイジーが事業活動を一切停止した時点から、などとするのです。一旦止めた後、競業行為を開始する元フランチャイジーも考えられることから、競業禁止の期間について、判決が確定した日から別途追加で起算されるというやり方も考えられるでしょう。
次に、イですが、これは、フランチャイズ契約上、競業避止義務違反や守秘義務違反があった場合の損害賠償額をあらかじめ定めておくという方法です。これらの違反の場合、違反行為が認定できたとしても、それによって一体いくらフランチャイザーに損害が生じたのかを立証することは難しいこともありますし、例えば、ロイヤルティ相当額が損害であるとした場合(これは通常容易に認められるものと思われます)、前述のとおり、差止請求自体に限界があるため、その程度の金額を支払えば競業行為ができるということになって、かえって元フランチャイジーに対し、違反行為を誘発することにもなりかねません。
そこで、フランチャイズ契約で、競業禁止行為の違反があった場合に、相応の金額(計算式でももちろんよいでしょう)を損害賠償額として定め、違反があった場合の損害賠償請求を容易にするとともに、元フランチャイジーに対して、違反行為をしないように思いとどまらせるという方法が通常とられることになります。これを法律的には「損害賠償額の予定」といいます。
ちなみに、これを定めた民法の条文は、以下のとおりです。
第420条(賠償額の予定)
一 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
二 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
三 違約金は、賠償額の予定と推定する。
損害賠償額の予定がなされると、請求する側は、損害がいくらあったのかを立証しなくてもよくなります。また請求された側は、損害が全くなかったことや、実際の損害額がそれよりも少ないことを立証したとしても、責任を免れることができなくなります。もっとも、損害が予定額より多かったとしても、多い金額を請求できるわけではありません(ただし、これについては契約上対処が可能です)。
損害賠償額をフランチャイズ契約で予定する場合、問題になるのが損害賠償額をいくらにすればよいのかということです。金額が多ければ多いほど、フランチャイザーにとっては有利といえますが、余りに高い金額を設定すると、裁判所に無効とされるおそれがあるからです。
ただ、そもそもフランチャイジーの側が違反行為をしなければ支払う必要のない金銭であること、余り低額だと、フランチャイジーの側にかえって違反行為を誘発することになることなどの理由からすれば、それなりに抑止効果のある金額を定めるべきではないかと思います。必須ではないですが、できれば、その金額を算定した根拠を示せるとよいでしょう。
フランチャイズマネジメント講座・公開講座のお知らせ
本年9月から、社団法人日本フランチャイズチェーン協会による「フランチャイズマネジメント講座」がスタートいたしますが、それに先立ち、無料の公開講座が実施されます。
開催日は平成24年7月27日(金)で、時間は午後1時30分から午後5時までです。
同講座で実際に講師をされる予定の講師陣の講義を直に体験できる貴重な機会だと思いますので、関心をお持ちの方は、是非ご参加下さい(先着20名までで、参加者の方には、講座の割引があります)。
詳しくは、日本フランチャイズチェーン協会までお問い合わせ下さい。