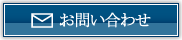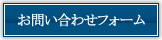新年あけましておめでとうございます
昨年は独立開業に伴い、多くの方に大変お世話になりました。
この場を借りまして、改めてお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今年は私にとっても真価を問われる年になると思います。
昨年以上に研鑽を積み、依頼者の期待に少しでも多く応えられるよう、頑張っていきたいと考えております。
手始めに、もう少し頻繁にこのブログも更新したいところです・・・
平成23年度下請取引適正化推進セミナーのご案内
下記の日程で、下請取引適正化推進セミナー(財団法人全国中小企業取引振興協会主催)の講師をいたします。
いずれも下請代金支払遅延等防止法と優越的地位の濫用を中心とした独占禁止法の解説で、有料(1名1会場14,000円)となります。
申込方法など詳しくは主催者ホームページ(http://zenkyo.or.jp/seminar/yuryo.htm)をご覧下さい。
記
1.平成24年2月24日(金)東京都江東区(東京ファッションタウンTFT)
2.平成24年3月7日(水)東京都中央区(日本印刷会館)
※時間はいずれも10:00~17:00です。
下請代金法トップセミナーのご案内
以下の日時・場所で、下請代金法トップセミナー(中小企業庁委託事業)の講師をいたします。
平成23年11月29日(火)埼玉県さいたま市
平成23年11月30日(水)栃木県宇都宮市
平成24年1月13日(金)名古屋市
平成24年1月17日(木)大阪市
時間はいずれも午後2時から5時までです。
詳しくは、http://www.shitauke-top.jp/をご覧下さい。
役務提供委託~「自ら用いる役務」について
下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます)という法律があります。とても形式的な法律で、当事者の資本金の額と取引内容によって適用の有無が決まり、適用がある場合、資本金の額の多い方が「親事業者」、少ない方(あるいは個人)の方が「下請事業者」となります。
親事業者になると、発注書面の交付義務などの4つの義務と、下請代金の減額の禁止などの11の禁止事項が課されることになります。
下請法の適用のある取引には、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つがあります。
このうち、役務提供委託とは、事業者が事業として行っている顧客へのサービス提供の全部又は一部を他の事業者に委託することです(ただし建設工事の下請は除かれます)。
役務とはサービスのことで、法律上は特にその範囲に制限がないため、あらゆるサービスが該当することになります。
この役務提供委託については、他の3つの取引と大きな違いがあります。それは、自ら用いる役務であれば、どのような場合であっても、それを他の事業者に委託する行為が役務提供委託には該当しないということです。
では、この「自ら用いる役務」とは、何でしょうか。下請法のガイドラインでは、「自ら用いる役務」に該当するかどうかは、「取引当事者間の契約や取引慣行に基づき判断する」としています。
これだけではわかりにくいので、例をみてみましょう。
公正取引委員会が作成している講習会用のテキストには、自ら用いる役務の例として
① ホテル業者が、ベッドメイキングをリネンサプライ業者に委託すること。
② 工作機械製造業者が、自社工場の清掃作業の一部を清掃業者に委託すること。
③ カルチャーセンターを営む事業者が、開催する教養講座の講義を個人事業者である個人に委託すること。
④ プロダクションが、自社で主催するコンサートの歌唱を個人事業者である歌手に委託すること。
を挙げています。
公正取引委員会がいいといっているのに、それに異を唱えるのは野暮なことだと実務家としては分かってはいるのですが、②はともかく、①、③、④はすんなり自ら用いる役務と納得しがたいものがあります。③でカルチャーセンターが聴講者に主に提供するサービスは何かといえば、「教養講座の講義」だと思いますし、④でプロダクションが観客に提供する主なサービスは、歌手の歌唱ではないかと思いますが、これらを他の事業者に委託していると考えられるからです。①については、どちらもあり得ると思いますが、宿泊中の宿泊客が希望する場合に行われるベッドメイキングの場合は、それがホテルの提供しているサービスの一部であることを否定するのは難しいのではないかと思います。
そこで、公正取引委員会の挙げている例から何かの法則(大げさですが)を帰納できるかを検討してみましょう。色々考えられると思いますが、他者に提供するサービスであっても、それだけ取り出しても意味をなさない、または、それだけ取り出すことができないサービスの場合には、自ら用いる役務になる、とはいえないでしょうか。
つまり、他者に提供する役務の一部を他の事業者に委託する場合とは、例えばある配送業者が顧客からAという荷物とBという荷物の配送を請け負った場合に、そのうちBの荷物の配送だけを他の配送業者に委託するような場合であって、他者に提供するサービスであっても、全体としてのサービスを構成する一部であって、そのサービスだけを取り出してみても顧客の要請を満たさないような場合には、「自ら用いる役務」といっていいように思えます。
これについて、①は分かり易いですが、③④でも、講義や歌唱の提供は、それが提供される場(会場)の提供その他のサービスと合わさってはじめて意味を持つものと考えられるでしょう。
次に、契約によって、自ら用いる役務にできる例をみてみましょう。
公正取引委員会のホームページに掲載されているQ&Aに、以下のような設問があります。
Q19 メーカーが,ユーザーへの製品の運送を運送業者に外注した場合には,下請法の対象となりますか。
A. メーカーがユーザー渡しの契約で製品を販売している場合,運送中の製品の所有権がメーカーにあるときは,当該運送行為は製品の販売に伴い自社で利用する役務であるため,役務提供委託には該当しません。
下請法の規制対象となる役務提供委託に該当するのは,他人の所有物の運送を有償で請け負い,他の事業者に委託する場合に限られます。
通常の運送業はともかく、例えば小売業者が客の購入した商品を配送する場合、その配送を他の業者に委託する行為が役務提供委託になるのかどうかは、特に配送がオプションであり、配送料を取る場合などにはにわかに判別しがたいところではないかと思います。ところが、この設問に従えば、商品の所有権の移転時期は契約で決めることができますので、契約で所有権の移転時期を引渡時とすれば、自ら用いる役務として処理できることになります(もっともこのためだけに所有権の移転時期を決めるのがいいかどうかの問題はありますが)。
なお、前記の基準によれば、購入者に対する配送サービスは、それだけ取り出すことのできないものと考えられますので、自ら用いる役務として処理できることになります。
以上
フランチャイズ・システムと優越的地位の濫用(2)
3.フランチャイズ・システムにおける「優越的な地位」と「濫用」の事例
以下では、平成21年6月22日付で、コンビニエンスストアの本部であるB社に対し、優越的地位の濫用に該当するとして排除措置命令が出されたケース(http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.june/09062201.pdf)について検討してみたいと思います。なお、この事件は、改正法施行前の事件になります。
(1)優越的な地位の根拠となった事実
B社については、以下のような事実をもとに、フランチャイジーに対して優越的な地位にあると認定されています。
①B社は、加盟者の合計が約12,000店舗、年間の売上額が2兆5700億円で、日本におけるコンビニエンスストアの最大手の事業者であり、一方、加盟社のほとんどすべてが中小の小売業者である。
②B社は、加盟者との間で使用を認める商標等に関する統制や加盟者の経営指導、援助の内容などについて規定した加盟店基本契約を締結している。この加盟店基本契約では、契約期間は15年とされ、原則として更新せずに終了することになっている。また、Aタイプ(加盟者が自ら用意した店舗で経営を行うタイプ)の加盟者は、契約終了後1年間の競業避止義務が課され、Cタイプ(B社が用意した店舗で経営を行うタイプ)の加盟者は加盟店基本契約書終了後直ちに店舗をB社に返還することとされている。
③B社は加盟店基本契約に基づき、加盟者が販売することを推奨する商品(推奨商品)及びその仕入れ先を加盟者に提示しているが、店舗で販売される商品のほとんどすべては推奨商品となっている。
④B社は、加盟者の店舗が所在する地区にオペレーション・フィールド・カウンセラーと称する経営相談員(OFC)を配置し、加盟店基本契約に基づき、OFCを通じて加盟者に対して経営に関する指導・援助等を行っており、加盟者はそれに従って経営を行っている。
ガイドラインの基準でいえば、①が本部の市場における地位と両者間の経営格差、②が取引先の変更可能性、③と④が取引依存度になると思います。フランチャイズ契約の期間が15年間もあるとはいっても、フランチャイザーからの中途解約権がないか、あっても制限されているかどうか、あるいは、推奨品の販売やOFCの指導がフランチャイザーの義務になっているかどうかについては全く触れておりませんので、実際に打ち切れるか不利益を加えられるかどうかを問わず、抽象的に取引を打ち切られたら困るといえれば、「優越的な地位」に該当するとの立場をとっているようです。ただし、取引を打ち切られれば確かに困るかも知れませんが、実際上取引を打ち切られるおそれについて十分に検討せず、いきなり加盟社はB社の要請に従わざるを得ない立場にあると結論づけるのは、少々言葉が足りないように思います。
(2)濫用行為
B社は、販売商品のうち、いわゆるデイリー商品は、B社の設定した推奨価格で販売されるべきとの考え方をとり、加盟者に対してその周知を図っているところ、加盟者が廃棄することとなった商品の原価相当額全額が加盟者の負担となる仕組みの下で、
①加盟者がデイリー商品のうち、販売期限が迫って来たものについて、値段を引き下げて販売するという、いわゆる「見切り販売」を行おうとしている場合には、OFCを通じてそのような行為を行わないようにさせる。
②加盟者が見切り販売を行ったことを知ったときは当該加盟者に対して見切り販売を再び行わないようにさせる。
③上記のような措置にもかかわらず加盟者が見切り販売をやめないときは、OFCの上司が加盟者に対し、加盟店基本契約の解除等の不利益な取扱いをする旨を示唆するなどして見切り販売を行わないようにさせる。
これらの措置によって、加盟者は、見切り販売の取りやめを余儀なくされており、それによって、加盟者が、自らの経営判断に基づいて廃棄になるデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせていると、公正取引委員会は認定し、これが、「取引の相手方の不利益になるように取引を実施」したことに該当するとしました。
この結論を導いた大きな理由が、フランチャイズ契約上、加盟者が加盟店で販売する商品の販売価格は自らの判断で決定するとされていたことではないかと思います。契約では自由であるはずの販売価格の決定を本部が優越的な地位を背景に妨げて、加盟者に不利益を負わせたことになるからです。
また、フランチャイズ契約の解除等を示唆したと認定されていますから、B社のフランチャイズ契約上(筆者はこれを見てはおりませんので推測になりますが)、本部からの中途解約権が規定されており、それがB社の優越的な地位の根拠となったとすると、結果として優越的な地位を認定したこと自体も、本件にあっては妥当だったといえるかも知れません。
4.実務上はどのように対応したらよいか?
では、フランチャイズ本部としては、優越的地位の濫用にならないようにするために、どのようにすればよいのかを最後に検討してみたいと思います。
① 当初の契約条件として明確化する。
フランチャイズ契約は、どうしてもフランチャイジーに対して様々な要請を行い、事業の遂行においても色々と制約を加えることになります。これは、フランチャイズ・システムの性質上やむを得ないものだと思いますが、前述のように、解釈の仕方によっては、割と容易にフランチャイザーにフランチャイジーに対する「優越的な地位」が認められやすいので、フランチャイジーの義務については可能な限り契約書上明確にするということが必要になります(なお、ガイドラインには、当初の契約条項であっても優越的地位の濫用が問題になるかのような記載がありますが、フランチャイズ契約を締結する際にフランチャイジーになる側が既にフランチャイザーに対して劣った地位にあるということは通常考えられませんので、妥当ではないと思います)。
上記のB社のケースでも、販売商品の販売価格について、契約書上本部の定める価格とすると決められていたら、B社の要請は、単に当初の契約条件を守れということになりますから、少なくとも、優越的地位の濫用が適用されることはなかったのではないかと思います。契約を守れということ自体は、正常な商慣習を持ち出すまでもなく当然のことだからです。
もっともこの場合、フランチャイザーによる価格統制の可否という別の独禁法上の問題が生じることになります。これもまた重要な論点となりますので、別の機会に論じてみたいと思います。
② 指示・指導の理由が合理的なものであるかをチェックする。
フランチャイザーが優越的な地位にあったとしても、フランチャイジーに不利益であれば、全く何の要請もできないわけではありません。それが正常な商慣習に照らして不当になされた場合に違法になります。このあたりガイドラインによれば、「フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施」するために必要なものか否かという点が一応の判断基準になるでしょう。
なお、フランチャイズ契約あっては、フランチャイザーに、フランチャイジーに対する一般的な指示や指導の権限が認められていることがあります。このような規定があれば、契約上の根拠があるということで、どのような指示・指導をしても良さそうですが、もちろんそう考えるべきではありません。何のためにそのような権限があるのかを考えれば、当然、それがフランチャイズ・システムによる営業を的確に実施するために必要だから、ということになるからです。
③ フランチャイジーに一定の出費、負担を強いるものについては、粘り強く交渉し、きちんと合意する。
フランチャイザーとして必要だと思うことについては、当初の契約書で規定していなかったとしても、システムに導入しなければならないこともあります。この場合、フランチャイジーに対しては、きちんと説明して納得の上、合意してもらうことが重要です。フランチャイズ・システムに必要といえる合理的な理由があるのであれば、フランチャイジーに本心から納得してもらった上で導入すれば、優越的地位の濫用とされるリスクはほとんどなくなるといってよいでしょう。
以上